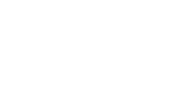M I C H E L L E > Autobiography (JPN)
Written by Michelle Branch:
ホント言うとこういうの書くのって大キライ。
いったい何て書けば人に自分の音楽を聴いてもらえるの?
何のためであれ、自分らしくないことはしたくない。
良かれ悪かれ見たまんまの私しかいないの。だからバイオってイヤ。
今まで成し遂げてきた素晴らしい偉業を書き並べ、
有名人の名前をちりばめて私を商品として売るわけでしょ。
でも今はまだそれはしたくない。
だからこれは私の輝かしくないバイオ。
「私と音楽との不倫話」。
「物心つくようになってからずっと、
そして家族が覚えている限り、私はいつも歌っていた」
私がお腹にいた時にどんな音楽を聴いていたのかと母に尋ねたら、
母は車の中でよくザ・ビートルズを聴いて口ずさんでいたと言った。
ザ・ビートルズが大好きなのはそのせいかも知れない。
ちなみに父はいまだに母がこの世で一番美しい妊婦だったと言っている。
私は予定よりも7週間も早く、1983年7月2日に誕生した。
体重はわずか3ポンド11オンス。
きっと世の中を見たくて待ちきれなかったのね。
私は今も全然変わってない。
記録に残っている最初の私の歌声は3歳のときのもの。
両親が大好きな歌を歌っている私を録音して祖母に送ったものだ。
私の音程は素晴らしく正確だった。
歌詞はまるでデタラメだったけど。
それもずっと変わっていない。
4歳から7歳まで私はザ・ビートルズの「Ticket To Ride」をずっと
“she’s got a chicken to ride” (彼女は乗り回すための鶏をもっていた)
だと信じて疑わなかった。
正しい歌詞を知ったときはがっかりした。
自分で作詞しようと決心したのはそのときだったと思う。
自分の歌詞のほうがずっと良いと思ったから。
いつもミュージカルを見てた。
とくに好きだったのは「オクラホマ」と「サウンド・オブ・ミュージック」
映画の登場人物になりきって歌詞を一言も違えずに歌った。
登場人物と同じような格好をして姉妹で家族の前でお芝居をしたり。
観客が大勢でなくても私はパフォームすることが何よりも楽しかった。
大きくなったらブロードウェイ・スターになるつもりだった。
その後人生が一変する体験をしたんだけど
正確に何歳のときだったかは覚えていない。
生死をさまよう重病にかかったわけでもなく、
未来の自分を垣間見るといった大げさなものでは全然ない。
ある時ニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックのコンサート・チケットが当たり、
私はいてもたってもいられないほどうれしかったの!
なんてったって毎日彼らのテープに合わせて歌って踊ってたから
(ちなみに私が人前で踊ったのはあのコンサートが最後だったと思う)
それのどこが“人生を変える出来事”なのかと
思うかも知れないけど、まあ聞いて。
あまりにクサくて吐きそうになっても我慢してね。
彼らをこの目で見て、人々に感動を与えている姿を見たとき、
私はただただ圧倒されたの。
鼓膜が破裂しそうでずっと耳を押さえ続けなきゃならなかったのも
へっちゃらだった。
コンサートの翌日、
彼らがなんと自分と同じホテルに泊まっていることが判明した。
私は女の子の群れの中を割って入って
(すごく小さかったのに押しつぶされなかったのが不思議)
バルコニーを見上げると、でっかいボディガードが見えた。
そのあとメンバーの1人が出てきて、私は興奮のあまり呼吸困難に陥った。
女の子の1人は彼にJolly Rancherキャンディを
投げてサインしてくれと頼んだ。
そのとき私は思った。
ミュージカル・ショーで歌うのではなく、ポップ・スターになりたい、と。
「両親は私の歌が趣味以上のもになっていることに気づき始めた。」
「ヴォーカル・レッスンを受けさせるべき」
と、他の子の両親がうちの親に薦めてくれた。
私もそうして欲しいと頼み込んだ。
そしてとうとうママとパパは北アリゾナ大学で
ヴォイス・レッスンを受けられるよう申し込んでくれた。
当時8歳だった。
私はカトリックの学校に通っていた。
制服はもちろんあったし、厳格なところだった。
毎週金曜日にはミサに行き、それが私に大きな影響をもたらした。
毎週金曜日は歌が歌える日だったから。
生まれてから11年間、私はアリゾナ州フラグスタッフに住んだ。
私も家族も雪と厳しい冬がイヤになって、
1時間南に走ったところにあるちょっとこじゃれた町に引っ越した。
それは私にとって願ってもないいい変化だった。
セドナは自然の美しさで知られる町で、とてもインスパイアされる環境だった。
音楽のレッスンはフラグスタッフの大学のままだったから
よそを探すことにしたのが幸いした。
探し始めてすぐに、Gina Betttumというヴォーカルの先生が
NYからセドナに移って生徒を探していることがわかった。
その先生についたことは人生最良の選択だった。
音楽業界にいた人だから私がまさに求めていた先生だった。
ソウルを込めてハートで歌うことを教わった。
それまでに身につけた技をやっと活かせる場を見つけたと思った。
先生は私の本来の声を見つける手助けをしてくれた。
ようやく第1歩を踏み出した気がした。
14歳の誕生日にギターが欲しいと親におねだりしたら、
なんと本当にもらえた!
(そういえば5歳のときに頼んだポニーはいったいいつ来るのだろう?)
叔父が兄弟の古いギターを持っていて、
私が気に入るかどうか試しに貸してくれた。
その翌日に初めて歌を作った。
両親に歌を作ったと報告したことを今も覚えてる。
ギターが弾けるとも思われていなかったから信じてもらえなかったのも当然。
詩を書いたりメロディを作るのが好きなのは知っていたけど、
その2つを合わすことができるとは思っていなかったみたい。
それから数ヵ月間私は自分の部屋にこもって
ギターを弾き、曲を1日中作り続けた。
新学期が始まると音楽に費やす時間が減ってしまうからすごくイヤだった。
学校は始まり、私はだんだん憂鬱になっていった。
でも、どんなネガティヴなものからもポジティヴなものって生まれるみたい。
だって私の親友でミュージシャン仲間のJenifer Hagioと出会えたのは
学校のおかげだったから。
学校に行くと私とジェンはいつも一緒につるんでソングライティングをしたり、
グラミーを受賞したらどんな衣装を着るかなんて話し合った。
気がつくと合唱、音楽、演劇、創作文学といった授業をとっている自分がいた。
数学の授業中はずっと曲を作ってた
(例えば「Sweet Misery」は代数Iの授業に作った)
その1年はあっという間に過ぎてまた夏がきた。
ジェンと私はハイスクールの1年を無事終わらせただけでなく、
レッド・ロック・ハイスクールのミュージシャンとして
同級生達に認識されるまでになった。
夏は音楽に集中し、フェスティバル、カーニバル、
アート・ショー、コンサートなどに出演できる季節だった。
次から次へと新しい曲のアイディアが生まれ、
紙に書き下ろすのが追いつかないほどだった。
ヴォーカルの先生の夫Garyにギターのレッスンをしてもらうようになった。
地元ではすっかり知られた存在になり、
ファンの年齢層が幅広いことに驚かされた。
レコード会社のスタッフが私のショーを観に来たり、
会う人会う人みんながいろんなツテを紹介してくれた。
プレイする会場も大きくなっていった。
私のやるべきことはこれだという運命を感じた。
自分の音楽を世界と分かち合い、
人々のインスピレーションになりたいと思った。
でも物事はそううまくは進まなかった。
約束したコールバックはまずかかってこない
デモを送った相手に期待してはいけない
屋外でプレイするときは髪を結ぶものをいつも持っていかなければならない
どんなにうまくても14歳じゃアリゾナ州の99.9%の会場でプレイできない
など思い知らされた。
誰も私の力を信じてくれなかった。
だから私はひたすら自分の腕を磨いた。
何かが起こる運命ならば、それを信じるしかないと思った。
無理したところで始まらない、と。
そうして夏は終わり、ハイスクールの2年目がスタートした。
音楽の授業の数は減り、クリエイティヴな授業はすでに取り尽くしていた。
曲を作る機会がなくなった。
私はただひたすら家にこもってギターを弾きたかった。
学校では“大人になったら何になりたい?”なんて質問され、
“大学や就職に備えましょう”なんて言われたり。
冗談でしょ、と思った。
私には音楽という立派な仕事があった。
“大人になったら”何をやりたいかははっきりしていたし、それに専念したかった。
だから学校を中退してホームスクーリングを選んだ。
そのとき私は15歳。
1999年1月2日、家族の知り合いから電話が入り、
デモ・テープと写真を持って近くのリゾートに来いと言われた。
彼女はLAから来た音楽業界の人のために
複数のバンドが出演するイベントを企画したと教えてくれた。
両親はちょうど不在だったから私は妹とジェンと一緒に
ゴルフ・カートに乗り込んで大急ぎで会場のホテルに向かった。
そこでJeff Rabhanと出会った。
彼にデモと写真を渡し、少し会話を交わした。
1週間が過ぎ、電話はなかった。
1ヵ月が過ぎ、電話はなかった。
そして2ヵ月が過ぎた。
あきらめた。
今までだって何度もあきらめたし、
電話を期待してはいけないのは分かっていた。
* 電話が鳴った *
「もしもし?」
「こんにちは、Michelle Branchはご在宅ですか?」
「私ですが」
「やあ、こちらJeff Rabhan。覚えているかい?」
というわけで今の私がいる。
偶然の出会いと1本の電話のおかげ。
あれから2年、Jeffは私のマネージャーで
私達はマヴェリック・レーベルと契約を交わしたばかり。
メジャー・レーベルからのデビュー作をレコーディングしている最中。
今最高にハッピー。
今までのたくさんの素晴らしい経験を振り返っても、
私にとって一番大切なのは人々が私の音楽にインスパイアされること。
心強いEメールを何百通ともらったわ。
「ついてない日にあなたの音楽を聴くと元気がでる」とかね。
そういうふうに言われるのが何よりもうれしい。
だからこのウェブサイトを作ったの。
ファンのみんなは私にこんなにも多くのものを与えてくれた。
だから夢をあきらめないで、心の信じるままに生きて。
いつあなたにも待っていた1本の電話がかかってくるかもしれないのだから。